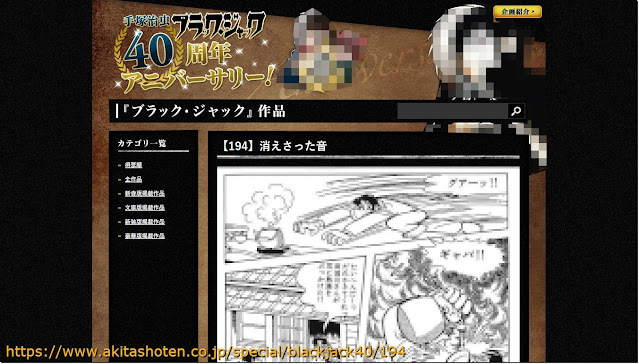「睡眠薬の正しい使い方」ビデオ by 慈恵医大

https://jikei-psy.com/zzz/ 「睡眠薬の正しい使い方」ビデオのご紹介 東京慈恵会医科大学の精神医学講座に以下のビデオがありましたので、ご紹介いたします。 慈恵医大 睡眠ビデオ 「睡眠薬の正しい使い方」ビデオ〜「睡眠薬減量のためのビデオの作成と動機付け効果」に関する研究 〜 | 東京慈恵会医科大学 精神医学講座 【睡眠薬の正しい使い方】慈恵医大 睡眠ビデオ① 0:00 プロローグ 1:07 睡眠薬は魔法の薬ではない 2:30 悪い事例(1)昔飲み始めた睡眠薬を止めそびれている場合 3:45 悪い事例(2)ご自身で不眠症を作っている場合 6:38 睡眠薬に頼らないコツについて 8:01 薬を減らすときの注意点 9:05 最後に 動画の感想 医療機関が睡眠薬の正しい使い方を患者向けに分かりやすく動画で説明していることに感心しました。 「睡眠薬は魔法の薬ではありません。」「睡眠はあなたの眠る力で眠っています。」これらは大切な説明だと思います。 睡眠薬の止め時について、睡眠薬を使い始めた時の問題が解消したら止めるよう説明されています。問題が明確でない場合もあるので、問題が解消したか判断しづらい場合もあります。 GABA-A受容体作動薬が含まれる睡眠薬は、身体的依存(GABA-A受容体の鈍化や減少)が緩やかに起きるので、長期間連用すると薬なしで眠るのが難しくなり場合があります。使用している睡眠薬を増やしたくなったり、もっと強い薬を求めるようになった時点で減薬を検討するのが良いと私は思います。 動画は10分以上と長めです。話す速度もかなりゆっくりで、眠たくなりました(笑)。動画の冒頭にどういう話をするか目次があると良いなと感じました。目次があると動画を見返すときにも役立ちます。 冒頭で紹介したサイトでは、アンケートを実施しています。アンケートに回答すると「睡眠ビデオのまとめ」が表示されます。 アンケートへのご協力ありがとうございました。 | 東京慈恵会医科大学 精神医学講座